一般診療から専門診療まで。チーム医療で飼い主に安心を届けたい
整形外科、循環器、画像診断など専門を活かしたチーム医療で、飼い主様にわかりやすい診療を行います。
- 古田 健介 院長

頼れる獣医が教える治療法 vol.025
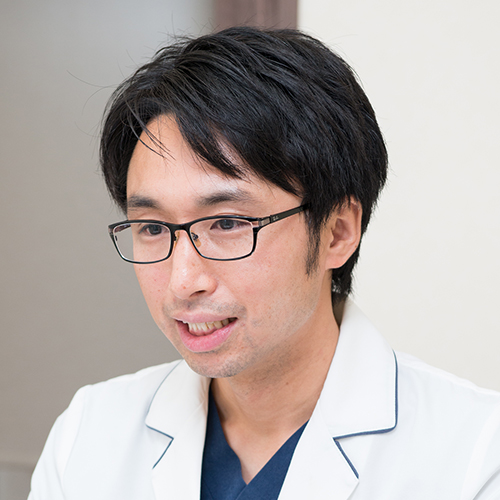
目次
はい、整形外科を専門的に学んでいます。神奈川の動物病院で勤務医として5年間、外科をメインに担当していました。その後に「難しい症例でも自分で対応できるようになりたい」と、母校であり二次診療専門である大学病院に戻り、研修医として4年間さまざまな経験を積みました。
整形外科では、まったく同じ症例や治療方法はありません。術後のレントゲン写真を見るだけで「こういう子だったな」と思い出せるほど異なっています。同じ前足の骨折であっても、折れている箇所や折れ方、年齢に合わせて最適な治療を検討しています。まだまだ学び足りていませんが、大学病院での経験を通じて提案できる治療のバリエーションと技術が身につきました。
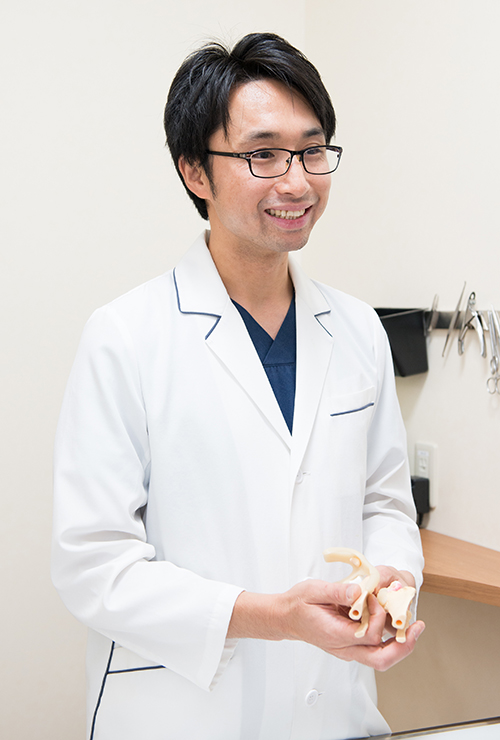
痛みの少ない治療を心がけています。整形外科の手術は、飼い主様の見えないところで行うので不安を抱えていることでしょう。だからこそ、飼い主様の信頼を裏切らないためにも疼痛管理は大切なのです。しっかりと鎮痛をしてから手術をすることで、痛みが少なく術後の回復も早い治療が可能になります。たとえば後ろ足の手術では、硬膜外鎮痛法により痛みを完全になくしてから手術を開始しています。人間の無痛分娩のようなイメージですね。
また、すぐに検査をするのではなく触診を大切にしています。まず、触診で「痛みの場所」「痛みの強度」を表情の変化を見ながら判断します。その後、客観的な評価を得るためにレントゲンやエコーを用います。「わかること」を積み重ねて手術を行うことが、犬猫自身の負担軽減に繋がります。

金属のプレートやピンで骨を直接固定する内固定と、患部の外側から固定する外固定に大きく分けられます。どちらの治療方法が良いかはその子により異なりますが、侵襲の少ない手術として創外固定も積極的に取り入れています。簡単に言うと、皮膚の外側からピンを打ち患部を固定する手術です。傷口が小さく負担が少ないことが特徴ですが、デメリットはピンを抜くまでエリザベスカラーの装着が必要になることです。外固定と内固定では、術後のケアの仕方や手術費用も異なりますので、それぞれのメリット・デメリットをお伝えして飼い主様に選択をしてもらいます。
骨は条件さえ揃えば治療をしなくても自然にくっつく組織ですが、それを手助けするのが僕たちの役目です。ただし、骨がくっついただけで「動かしにくい」「曲がっている」という状態では、本当の意味で治ったとは言えません。当たり前のことですが「正しく治しているのか」を常に自問自答しながら治療を行っています。

レッグペルテスは「大腿骨頭壊死症」とも呼ばれ、成長期の小型犬で多く見られます。股関節部分にある大腿骨の骨頭の血流が阻害され、骨が壊死し形成不全を起こす病気です。原因は分かっておらず、若齢の子のみに起こります。歩くときにケンケンやスキップなどの跛行が見られたら要注意です。慢性的に痛みが伴うと左右の足で筋肉の付き方も変わってきます。
鎮痛剤でコントロールできるケースは少なく、多くの場合は痛みの原因である骨頭を取り除く「大腿骨頭切除術」を行います。関節の一部を取ることに不安を感じるかもしれませんが、骨頭を切除しても靭帯や筋肉が骨をしっかり支えますので、元気に歩いたり走ったりできるようになります。手術時間は30分程度で、3,4日の入院を要します。手術後は安静にしなければいけないですが、その後は無理をしない程度に足を動かしリハビリをすることが大切です。

こちらも小型犬で非常に多いですね。膝のお皿が外れてしまう病気です。膝の動き方によって、4段階のグレードに分けられます。症状が進行してグレード3や4になると手術が必要になるというわけではなく、「痛み・違和感があるか」「びっこをひいているか」といった症状の有無で手術の可否を判断します。グレード1でも、お皿が外れた時の痛みが強く出たり繰り返し外れたりするようであれば、手術を行うこともあります。
症状が出ていなかったとしても、健康診断やワクチン接種のときに見つかることもあります。数か月齢の仔犬の場合、そのまま成長すると骨が変形して歩行が困難になる可能性もあるため、治療内容の判断を慎重に行います。すぐに手術が必要ない場合には、5年後、10年後の予測や家庭での気を付けるポイントをお伝えしています。


横浜青葉どうぶつ病院 地図を見る
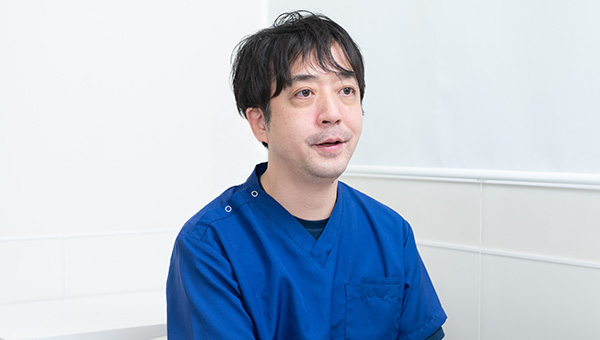
初期には無症状であることも多い、犬や猫の肝疾患。血液検査や画像診断、腹腔鏡下での検査が有効です。
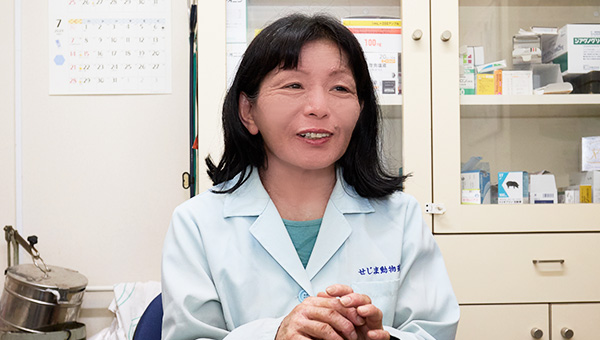
低侵襲のレーザー治療と漢方・鍼灸などの東洋獣医学を組み合わせ、ペットとの幸せな時間に貢献します。

異物誤飲して開腹手術を勧められた? その決断ちょっと待って! 切らずに内視鏡で解決しましょう!