日常的な動作でも発生する、小型犬の橈尺骨骨折・椎間板ヘルニア
「ソファから落ちた」などでも発生する、小型犬の骨折。ちょっとした違和感でもお早めにご相談ください。
- ノア動物病院 北海道札幌市豊平区
-
- 平子 毅 院長
- 田村 雄治 獣医長

頼れる獣医が教える治療法 vol.059

目次
咳や呼吸の苦しさ、鼻水、くしゃみ、いびきなど、鼻から肺までの呼吸に関わるすべての症状を診ています。セカンドオピニオンでは、なかなか咳が治らない、レントゲン検査で「肺が白い」「気道が狭い」などの異常が見つかった、というケースが多いですね。ワンちゃんネコちゃんの患者さんは同じぐらいです。気管虚脱や短頭種気道症候群に対しての手術も実施しています。
呼吸器科専門外来は予約制です。呼吸器の病気は同じ症状であっても治療法が異なることが多いので、呼吸器科の診療では、可能な限り確定診断を行う、つまり病気を特定することが何よりも大切です。

問診を綿密に行い、そのあとに身体検査やレントゲン検査、血液ガス分析、内視鏡検査などを実施します。
問診では見落としがないように「呼吸は吸いづらいのか吐きづらいのか」「どのタイミングでどんな音の咳をするのか」など、様々なことをお伺いします。初診では30~60分程度お話を聞いて、病変部位と病気を推測します。またレントゲン検査では、静止画だけでなく動画のように撮る透視検査という手法も用いて、気管支や喉の動きを確認します。特殊な検査では、肺機能を調べる動脈血ガス分析や、麻酔下での気管支鏡や鼻鏡による内視鏡検査も状況に応じて実施します。

短頭種の子では「鼻の入り口が狭い(外鼻孔狭窄)」「鼻の中が狭い(鼻腔狭窄)」「軟口蓋が長い(軟口蓋過長)」「軟口蓋が分厚い(軟口蓋肥厚)」「気管が細い(気管低形成)」といった骨格的、解剖学的異常が多くみられ、それらが合わさって起こる症状を短頭種気道症候群と呼びます。代表的な症状はいびきや呼吸困難です。パグでも鼻の通りのよい子がいるように、すべての短頭種が罹患するわけではないですが、短頭種の飼い主様には知っておいてほしい病気です。
軽度の場合は体重管理など内科的なケアを行いますが、根本的に解決するには手術が必要となることがあります。短頭種は麻酔から覚めたあとに上気道閉塞(窒息)を起こすことがあるので、術前にそれらのリスクについても十分に評価したうえで、症例毎に必要な治療として「鼻の穴と、その中を広げる」や「軟口蓋の長さや厚さを整復する」「喉にできた喉頭小嚢を取る」などの手術を行います。短頭種気道症候群としての症状が認められるのであれば、病態が進行してしまうことの多い4歳までの治療を推奨しています。いびきや日常的なガーガーやブーブー、ズーズーといった呼吸音が当たり前だと思わずに、気になる症状があればご相談いただきたいです。

気管が潰れることで様々な症状がでる病気です。軽度の段階では咳がみられ、重度になると「ガーガー」「ゼーゼー」というアヒル様やガチョウ様呼吸と表現される呼吸困難を示します。気管が潰れる原因は分かっておらず、小型犬で好発しますがどの犬種でも発症します。
気管虚脱はレントゲン検査で発見しやすい病気ですが、「手術が適しているタイプ」と「内科治療が適しているタイプ」に分かれることはあまり知られていません。気管がどのように潰れているのかどうかを見極めることが治療のカギです。

気管は軟骨と膜で構成されているのですが、軟骨が潰れていても膜が伸びていても、レントゲンでは同じように見えてしまうので、透視検査や気管支鏡検査によりどのように気管が潰れているかを診断します。軟骨が潰れて扁平化している場合には手術が有効です。一方、膜が伸びて潰れているタイプは気管以外の部位に原因があるため、そこの治療をしないと治りません。多くの場合は内科治療が適しています。

気管内にメッシュ状の金属を入れて内側から広げる気管内ステント留置術と、気管の外にコイル状の補強材を取り付け外側から広げる気管外プロテーゼ術の2通りの方法があります。ステント術は、皮膚の切開は不要で数分の手術で呼吸困難を解消することが可能です。しかし、定期的な検査やネブライザー療法などの自宅での日常的なケアが必要になります。気管外プロテーゼ術は、合併症がなければ一回手術をするだけでその後のケアは必要ありません。ただし手術時間が長い、手術が難しく実施している病院が限られている、といった難点もあります。
当院ではどちらの手術も実施できますが、それぞれにメリット・デメリットがありますので、ワンちゃんやご家族のご事情などを考慮して最善の治療を提示するようにしています。手術方法や費用などなんでもご相談ください。


名古屋みなみ動物病院・どうぶつ呼吸器クリニック 地図を見る

「ソファから落ちた」などでも発生する、小型犬の骨折。ちょっとした違和感でもお早めにご相談ください。
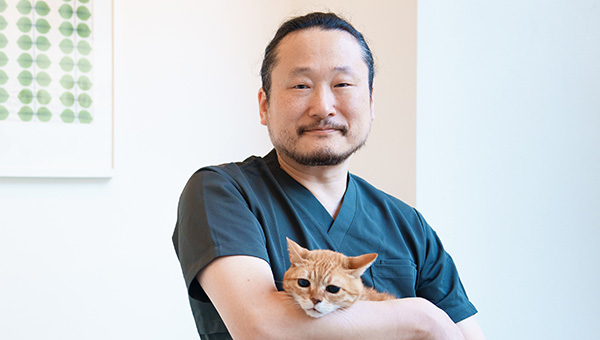
ジェネラリストとして幅広い分野で技術を磨き、家族目線でその子にとってのベストを一緒に考えます。
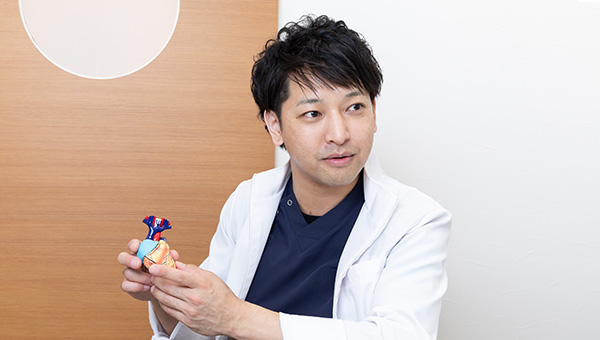
獣医循環器認定医が行う心臓病の治療。犬・猫、飼い主のライフスタイルに合わせた治療を提供します。