定期的な検診で、猫の「肥大型心筋症」を早期発見・早期治療
猫に多い心臓病「肥大型心筋症」は、予防も完治もできません。検診により、症状が出る前に発見しましょう。
- 緑の森どうぶつ病院 さっぽろ病院 北海道札幌市中央区
-
- 森 伸介 院長

頼れる獣医が教える治療法 vol.056

目次
根尖周囲病巣という根尖(歯の根っこの先端)で起こる病気の一種で、膿が溜まった状態を根尖膿瘍と言います。破折(歯が折れる)や歯周病などが原因となり歯の髄が障害を受け、歯髄炎、歯髄壊死と進行していき、根尖で膿瘍を作ります。歯髄炎の段階では痛みがありますが、壊死すると痛みがないため、飼い主さんが初期段階で気づくことは難しい病気です。悪化すると、膿が溜まって目の下がぼこっと腫れる、皮膚や口腔内に歯瘻(膿の出口となる穴)ができるなどの症状が現れ、下顎の骨が折れる場合もあります。
歯科レントゲンを撮らないと事前に診断することが難しいケースもあり、通常の歯周病の抜歯と思って治療を進めると思わぬ出血や骨折を起こすこともあり得えます。ですから、根尖膿瘍などの根尖周囲病巣を疑う場合は、飼い主さんと獣医師でしっかりと相談して検査・治療方針を決めることが大切です。

根尖周囲病巣は歯の根っこに起こる病気なので、レントゲンを撮らないと診断できません。
最初に視診を行い、歯の病気である可能性が高ければ麻酔をかけて歯科用レントゲンを撮り、根尖とその周囲の骨の状態を確認して診断します。
顔が腫れている子では皮膚病と誤診されて転院してくる子もいます。膿瘍も細菌感染を起こしていることが多いので抗生物質を投与すると一時的に腫れは引きますが、原因が除去されないので何度も再発してしまうのです。また、硬い物を噛んだり、噛み合わせが悪く歯が当たったりすることで徐々に歯が削れる咬耗や、エナメル質のヒビから細菌感染が起こり歯髄炎になる場合も、歯の病気だと気づきにくいケースです。病変の見逃しがないように注意深く診ることが重要です。

その子の状態に応じて治療方法を選択します。根尖病巣の程度によっては、歯の中の血管や神経を除去し、歯髄をクリーニングして歯を残す「歯内療法」を行います。歯内療法が適応でないケース、たとえば根尖周囲病巣や重度の歯周病などで骨融解を起こし、下顎骨が骨折している場合は「抜歯」を行い、同時に感染している顎の組織を処置することで治療します。

歯を残すメリットは、見た目が変わらず、ワンちゃん自身が噛むことを楽しめること。デメリットは病気の再発や進行するケースがあり、定期的なレントゲン検査が必要なことです。特に歯周病が原因の場合、デンタルケアが十分にできないと、再発に加えて他の歯にも炎症が広がり、数か月後には抜歯が必要となるケースもあります。
飼い主さんに歯を残すことのメリットとデメリットを認識してもらったうえで、ご希望に寄り添って治療を提案するように心がけています。

歯科用レントゲンを撮り、飼い主さんと画像を見ながらディスカッションして治療方針を決定します。これは、「こんなにひどいなら抜いてほしかった」「この状態なら残して様子を見たかった」といった後悔や、飼い主さんと獣医師との間での判断のギャップを防ぐための工夫です。麻酔の回数を減らすためにレントゲンを撮影しない、もしくは撮影と同時に処置を行う、という考え方もあるとは思います。しかし、当院ではレントゲン画像を見ながら相談して最終決定することが、動物と飼い主さんにとって将来的に良い結果を生む治療につながると信じています。
歯科治療は、ベースは病院、デンタルケアは飼い主さんが行う二人三脚の治療です。治療をするからには、動物には良くなってほしいですし、飼い主さんにも「前よりケアがしやすくなった」と思ってほしい。抜歯でも歯内療法でも、処置後の自宅でのデンタルケアを具体的にイメージできるようにお伝えして、なるべく飼い主さんがケアしやすい内容を提案しています。

動物の性格によっても受け入れてくれるケア用品は異なるので、その子に合わせた方法で行ってください。歯ブラシだけではなく、ジェルやガムなどさまざまなデンタルケア用品がありますので、どれを使うか決めていきましょう。
3歳以上の犬猫の8割は歯周病であると言われます。当院では最低年1回の歯周病検査や治療を推奨しています。歯科用レントゲンが撮影できればベストですが、麻酔を必要としない歯周病菌のリスク検査などもあります。動物と飼い主さんが無理しすぎない方法で、口腔環境を維持できるように一緒に考えましょう。


かしわだい動物病院 地図を見る

猫に多い心臓病「肥大型心筋症」は、予防も完治もできません。検診により、症状が出る前に発見しましょう。

高度な医療に身近な相談まで、「寄り添う診療」を人と動物へ提供。複合施設「ハルニレほっぽ」も魅力です。
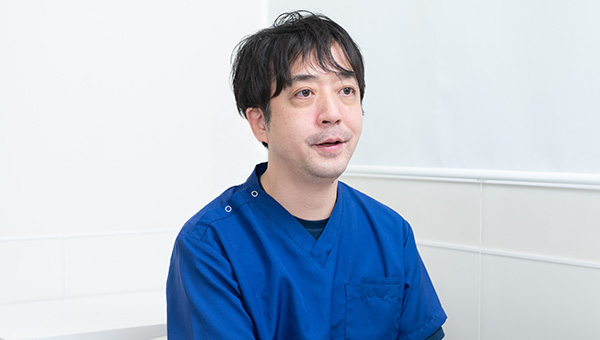
初期には無症状であることも多い、犬や猫の肝疾患。血液検査や画像診断、腹腔鏡下での検査が有効です。