犬猫の肝臓機能低下に対する診断と「門脈体循環シャント」の治療
初期には無症状であることも多い、犬や猫の肝疾患。血液検査や画像診断、腹腔鏡下での検査が有効です。
- 船橋どうぶつ病院 千葉県船橋市
-
- 守下 建 院長

頼れる獣医が教える治療法 vol.030

目次
肝臓病とは、なんらかの原因によって肝臓の機能が低下して障害があらわれる病気です。嘔吐や下痢、食欲不振、おしっこの色が濃くなる黄疸などが頻発所見ですが、肝臓病だけにあらわれる特徴的な症状はありません。「なんとなく元気がない」ことがきっかけで来院されて、検査をして発覚することが多いですね。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほどダメージに強く症状が出にくいため、気づいた時には病気が進行しているケースがほとんどです。しかし、症状が出る前に健康診断で見つかりやすい病気でもあります。

肝臓病には、悪性腫瘍である肝臓がんや良性病変である過形成、慢性肝炎などさまざまな種類があります。画像診断や血液検査では病気を特定することはできず、確定診断をするためには肝臓の組織を採取し病理検査を行うことが不可欠です。
肝臓は胃と横隔膜の間にある臓器で、犬の場合は6つの肝葉に分かれています。検査により肝臓病であると診断がついても、肝臓のどの場所に病変があるか、悪性か良性かなどは肝臓に直接アプローチしないと特定ができません。重要な血管が多く手の届きにくい場所にあるため、手術が難しい臓器でもあります。そのため手術が敬遠され、投薬治療で様子見をされやすい病気ですが、早期に的確な治療を開始することで予後が大きく変わります。

まず血液検査やレントゲン、エコー検査など各種検査を行い「肝臓病である」という診断をつけます。肝臓病と特定できたら、飼い主さんと相談して治療方針を決定しますが、肝炎の場合は投薬だけで治る場合もあります。
手術を行うことのメリットは、病気の確定診断をすることで的確な治療ができることです。肝臓がんの場合では、切除をすることで完治が見込めます。ただし、手術により必ず治るわけではありませんので、手術内容を事前に飼い主さんにしっかり説明して、手術に立ち会ってもらうこともあります。

肝臓にできた悪性腫瘍は、肝臓内で発生する原発性と、転移性の2つに分けられます。転移性とは、他臓器から転移して肝臓にもがんが発生するケースです。ヒトの肝臓がんと異なり、犬の肝臓がんは転移をせず局所で起こるものが多いことが特徴です。ですから、がんを完全切除することができれば完治が見込めます。治療方法は主に手術か抗がん剤治療の2通りです。
飼い主さんの中には「自分のせいでがんになってしまった」と思い悩む方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。一般的に肝臓がんは高齢になってから発症します。「上手に飼って、長生きしているからこその病気である」と言えるでしょう。

原発性で肝臓だけに限局している場合、完全切除により完治します。肝臓は再生能力が高いので、切除をした部位も時間が経てば元通りになります。転移性の場合は手術を行うべきではありません。転移性かどうかは術前検査で判断できます。
当院では、肝臓の手術を行う際には積極的に飼い主さんに立ち会ってもらっています。実際の肝臓を見てもらうと、色やツヤ、形などから普通ではないことが分かるからです。獣医師は「この治療をしたら病気がどうなるか」という予測がつきますが、飼い主さんは手術によるメリットを想像するのが難しいこともあると思います。肝臓病では、お腹を開けてはじめて「悪性なのか良性なのか」「がんを完全切除できるのか」がわかるので、不安に思われるのは当然のことでしょう。僕たちは、手術をすることのメリットがデメリットを上回ると判断した時に、手術の提案をしています。手術のリスクや費用面など、気になることは何でもご相談ください。

どんな病気であっても、獣医の話し方ひとつで飼い主さんの治療への向き合い方が変わります。お茶を濁すような診療を行えば、飼い主さんは治療内容に不安を抱きます。たとえば肝臓病では、手術をしなければ確定診断をすることができません。もちろん完治が難しいという結論になる場合もありますが、病気の原因がわかるのも重要だと考えています。確定診断がつかないと治療方針がぶれますし、飼い主さんにも「もっと良い治療があったのではないか」と後悔が残ります。飼い主さんに「やりきった」と感じてもらえるような診療をしたいと思っています。


えびす動物クリニック 地図を見る
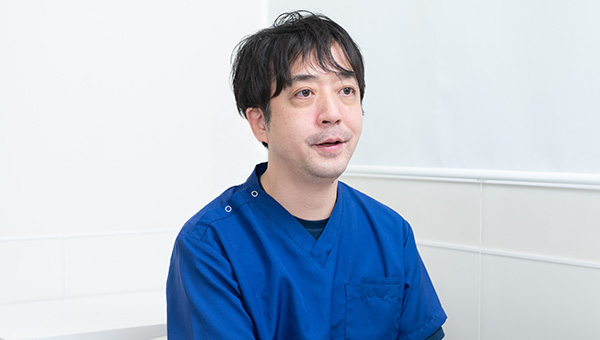
初期には無症状であることも多い、犬や猫の肝疾患。血液検査や画像診断、腹腔鏡下での検査が有効です。
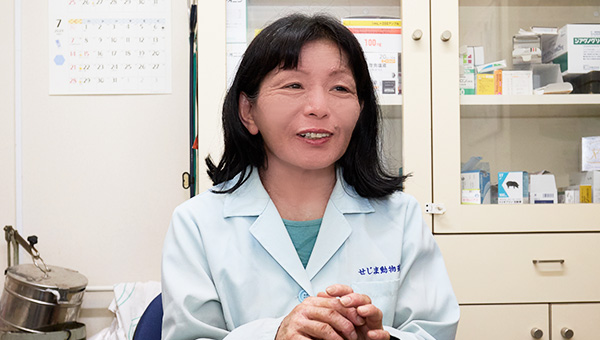
低侵襲のレーザー治療と漢方・鍼灸などの東洋獣医学を組み合わせ、ペットとの幸せな時間に貢献します。

異物誤飲して開腹手術を勧められた? その決断ちょっと待って! 切らずに内視鏡で解決しましょう!