飼い主さんとの対話を大切に、家族目線で医療を提供したい
ジェネラリストとして幅広い分野で技術を磨き、家族目線でその子にとってのベストを一緒に考えます。
- めい動物病院 神奈川県川崎市中原区
-
- 竹内 潤一郎院長

頼れる獣医が教える治療法 vol.010

ペットの口臭で一番多い原因は歯周病です。しかし、がんや内臓疾患などの全身的な疾患から口臭があることもありますので、まず全身の健康診断を行います。歯周病に関しては歯垢や歯石が付いていて、歯茎(はぐき)の腫れがある子は要注意です。

犬や猫の場合は人間とは違って、毎食後や一日に何回もこまめに歯磨きなどのケアをすることが難しいので口の中の歯を中心に歯石や歯垢がついてしまいます。汚れがたまると臭いの原因になったり歯茎が腫れたりといった症状がでてきます。歯周病は、歯肉に炎症がある歯肉炎と、歯を支える骨にも影響がでている歯周炎とに段階が分けられます。歯周病になるとペットの場合も人と同じような症状がでます。
犬では3歳以上の子の75%が歯周病になっていると言われています。猫の場合ですと、ヘルペスウイルスやカリシウイルスなどの感染症が原因でもっと若いうちから歯周病になっている場合もあります。歯石の付き方が気になりはじめるのは3、4歳からですが、歯茎のトラブルはもっと前から起こっていることが多いです。
歯周病は進行すると歯と歯茎の間にある歯周ポケットに汚れが詰まってきて、細菌が増え歯周ポケットは深くなってしまいます。進行すると歯茎が痩せる、痛みがでるだけでなく、歯の根っこにも影響を与え最終的には歯が抜けてしまうこともあります。
症状の出方は動物種や性格によって異なりますが、頭を振ったり傾けたり、食べる勢いがなくなったり、硬いフードを嫌がる子もいます。犬の飼い主さんの場合は、ご飯の食べ方やフードの好みの変化に気付かれる場合が多く、猫の飼い主さんの場合はご飯を食べなくなったり、よだれの多さや歯ぎしり、叫び声で気付かれたりする場合が多く感じます。共通しているのは口臭の強さです。
口腔以外への影響としては、細菌が血液をたどって全身に回ってしまうので、肝臓や心臓などにも悪影響を及ぼすことがわかっています。

歯周病ケアのやり方がよく分かっていなかったり、ケアの仕方が不十分で伝わっていなかったりすることが歯周病を防げない原因になっていると思います。
歯周病は食べ物や環境など日常生活の中で出てくる色々なことが原因でおきます。これだけをケアすれば大丈夫ですと特定することはかなり難しいです。人間もデンタルケアをしなければ歯周病になってしまいます。それをいかに防ぐかということがとても大切です。
歯周病は遺伝的なことよりも、環境的なことが原因になることが多いと考えていますが、犬は種類によって顔の形が大きく異なるため、ダックスフントなど顔が長い犬種が歯周病になりやすいということはあります。また、大型犬よりも小型犬の方が歯周病になりやすいとは言われています。
しかし、大型犬でも硬いものをかじる子は歯が折れてしまったり、ボールをいっぱいかじる子は歯が削れてしまったりと歯のトラブルはよくおきます。
日々の診察では口の中を触られることを嫌がる子が多いですので、ストレスが少なくて済むように、口の中はなるべく短時間でしっかりとチェックするように心がけています。そのために、事前に動物の種類や年齢、飼い主さんとのお話から性格や日々の習慣などを確認して、歯周病になりやすいかどうかを予測しています。
フードについていえば、缶詰や手作り食などやわらかいものや歯に絡みやすいものは口の中に残り汚れの原因となることもあります。最近では繊維質が多く歯の汚れを絡みとってくれるデンタルケアにも配慮したフードも出ています。

歯周病のケアという意味でいうと、病院でしかできないことと、ご家庭でできることの大きく2つに分かれます。病院でしかできない治療は歯垢や歯石をきれいにし歯周ポケットの汚れを取り除くことです。歯や歯周ポケットの間の汚れを除去するスケーリングや、スケーリングをした後で一見きれいになっているようですが残っている細かい傷などを磨いて整えるポリッシングという処置を行います。汚れがつきにくくなるように処置を行い病院でしかできない処理は終了です。
歯周病のケアは病院でできることより、ご家庭でするケアの割合が圧倒的に多いので、病院で歯石を取っておしまい、ということではなくて、そこからが歯周病ケアのスタートになります。どのように自宅でケアができるかを提案することがとても重要だと考えています。

歯と歯茎の重症度にもよりますが、歯石を取ったり歯茎をきれいにしたりする処置は、全身麻酔をかけますが日帰りで終わります。あとは病院で定期的にチェックをすることと自宅でケアを行うことになります。病院での処置はあくまで酷い状態を元に戻すためのリカバリーですので、繰り返しにはなりますが、歯周病ケアは病院で歯石を取っておしまいではなく、自宅に帰ってからのケアが大切です。病院で歯石を取ったからケアが終わったと思われる方が多いのですが、きれいになった状態を自宅でのケアによって維持する期間が重要になります。

自宅でどれくらいケアができているかということや、同じ生活環境でもその子ごとに歯の丈夫さが異なりますので、定期的にチェックをして相談しながら決めています。汚れのつきやすい子ですと数か月ごとにケアにいらっしゃる子もいらっしゃいますし、病院での処置を数年行わなくても平気な子もいらっしゃいます。
麻酔に関してですが、皆さん麻酔に対する恐怖心が強く「高齢だから麻酔ができないのではないか」「麻酔は安全なのか」と質問される方が多いのです。もちろん、その子の状態によって答えは異なるので、麻酔前にしっかりと検査、説明をさせていただき、相談させていただきます。
一般的には全身状態に問題がなければ高齢の子でも麻酔は使えます。実際には、人間でも犬や猫でも、全身麻酔をかけて行う処置や手術の機会は、若い頃よりも高齢になるほど増えるといえます。
犬や猫は高齢になると口の中が悪くなって歯周病になっていることが多いので、例えば15歳を超えた子でも麻酔を使用して治療を行うこともあります。麻酔をしないで歯周病治療を行いますと外から見える歯石は除去できてもしっかりとしたケアができないので、歯周病の治療としては不十分な処置となります。
麻酔をかけることが危険な場合には、麻酔をかけないで行えるお口のケアを飼い主さんと一緒に考え、相談させていただいております。

歯周病の予防で大切なことは、まず気づいてあげることです。わんちゃんや猫ちゃんのお口が臭っていたり汚れていたりすることに気づいている方はとても多いです。そしてその状態がよくないことだとわかっている方も多くいらっしゃるように感じます。ですが、実際に何かお口のケアをされている方はとても少ないです。毎日ケアをされている方となると1割もいらっしゃらないと思います。
皆さん口の中はチェックしているけれど、実際に何をすれば良いかわからなかったり、ケアをしようと思ったものの途中で挫折してしまったりされることが多いのではないかと思っています。
自宅でできるケアとして、まず唇をめくって歯茎の色や歯についている汚れ、においなどの状態を確認することから始めてください。口を触られることを嫌がるわんちゃん猫ちゃんは口を触られることに慣れさせることから始めることが大切です。慣れてきたら口の中を触ってみて、べたつきがあるかを確認したり、歯茎の腫れや出血がないか、歯茎が減って歯の根元が見えていないかなどのチェックをしたりします。
食事の時の様子の変化も気づきやすいポイントだと思います。食べにくそうだったり、ポロポロこぼしたり、色々な形で変化が見られると思います。気になったことは動物病院に聞いてしまうのが一番です。

ケアで一番効果的なのは歯ブラシです。歯の表面や歯周ポケットの汚れを直接除去することができます。また歯周病の原因となる細菌は空気の少ないところを好みますので歯周ポケットに空気を入れることで歯周病の原因菌の繁殖を防ぐことができます。
歯ブラシ以外にもガーゼやデンタルジェル、デンタルリンス、ガムやサプリメントもデンタルケアになります。それぞれの道具で目的が異なりますので組み合わせることが大事です。
例えば、歯ブラシやガーゼなどを使用して指でケアを行うと、前歯は磨きやすいのですが、奥歯をしっかりと磨くことが意外と難しいことに気付かれると思います。また、ガムをかじっている様子をよく見てみると、多くの場合は手でガムを抑えたりしながら奥歯で一生懸命にかじっている姿が見られると思います。わんちゃんや猫ちゃんには歯を磨こうという意識はありませんので、前歯ではなく、力の入りやすい奥歯を使うのです。ですので、ガムだけでは前歯のケアは不十分といえます。
歯を直接的に磨く方法以外にも、口内環境を整えることでデンタルケアを行う方法もあります。デンタルジェルや飲み水に混ぜるデンタルリンスは手軽にできるケアの1つです。ジェルやリンスには殺菌作用があり、菌の繁殖を抑えることができます。また、近年では飲むだけでお口の中の善玉菌を増やし口内環境を整える錠剤タイプのサプリメントも売られています。
様々な商品がありますので、いくつかの道具や方法を組み合わせることでよりよいデンタルケアが可能となります。
また、デンタルケアに関して注意があります。実は日常のケアで良かれと思ってやっていることで、歯にダメージを与えている場合がよくあります。硬いおもちゃや骨、アキレス腱などのおやつをあげることもあると思いますが、顎の力が強い子や一生懸命噛みすぎてしまう子ですと、歯垢がとれるだけでなく歯が削れたり折れてしまったりすることもあるのです。意外に知られていないので、歯が折れてしまっている子を見かけることは少なくないです。

まず認識として、はじめから歯ブラシをさせてくれる子はほとんどいません。よく飼い主様から、「口の中をケアしようと1週間頑張ったけれどうちの子は口を触らせてくれない、デンタルケアができない子なんだ」とのお声を聞きます。実際に数週間でデンタルケアがしっかりできるようになる子は少ないんです。
歯ブラシができるようになるには数か月はかかると思ってください。まずは口を触る練習から始めて、徐々に慣れてきたらジェルを舐めさせてみる。次に指をつかって口の中にジェルを塗ってみる。今度はジェルをつけた指で歯を撫でてみる。そして、少しずつ歯ブラシを使ってみる。というように、できることを増やすことが大切です。
文章で書くと簡単ですが、一つ一つの手順に1~2週間以上かけてゆっくりゆっくりやっていくのが失敗しにくいコツだと思います。
デンタルケアを始めるときに、気合を入れて毎日歯ブラシをしようとすると、ペットたちもご家族も疲れますしお互いに嫌になって続かなくなってしまうことが多いです。はじめから毎日ケアを行う必要はありません。週に1、2回でも口を触る練習からはじめて徐々に慣れさせていくことが重要です。
歯みがきができないことで、ご家族の方はがっかりしないでください。普通はできません。その子のペースで数か月単位の長期スパンで練習を重ねることが大切です。
それに、どうしてもデンタルケアに時間を割けない場合もあるでしょう。心配しないでください。今は色々な道具があるので、歯ブラシができないといって、時間が割けないと何もできないわけではありません。その子にあったケア、お家にあったケアを相談して始めてみましょう。

お口の治療が終わると、ご家族みんなに喜ばれることが嬉しいですね。お口が汚れていた時には、「口が臭いからあっちにいって」とか「舐めないで」と言われていたわんちゃんが、臭いもなくなって飼い主さんも嬉しいし、笑顔の家族を見たわんちゃんも嬉しい。動物病院をやっていてよかったなぁと思います。
高齢になったからボール遊びをしなくなったのかと思っていたら、歯周病の治療をしたら元気に遊ぶようになったという子や、治療をしたらご飯をバクバク食べるようになったなんて話もよくあります。
食事は生活の基本であり、体の基本です。人間もそうですが、わんちゃん、猫ちゃんも歯が痛くて元気がないとか、食欲が出ないということは意外に多いのだと思います。
他にも歯周病が原因でくしゃみや鼻血がでてしまう子も多いのですが、軽い症状であれば問題なくても、酷くなるとご家庭は大変です。床も家具も汚れてしまう。そのような場合も治療後に症状が治まって、大変喜ばれるので嬉しいです。
お口の悩みに限った話ではないですが、困りごとや心配が解決して喜んでいただく姿、ご家族の笑顔と喜ぶ動物の姿を見るのは最高に嬉しいことです。
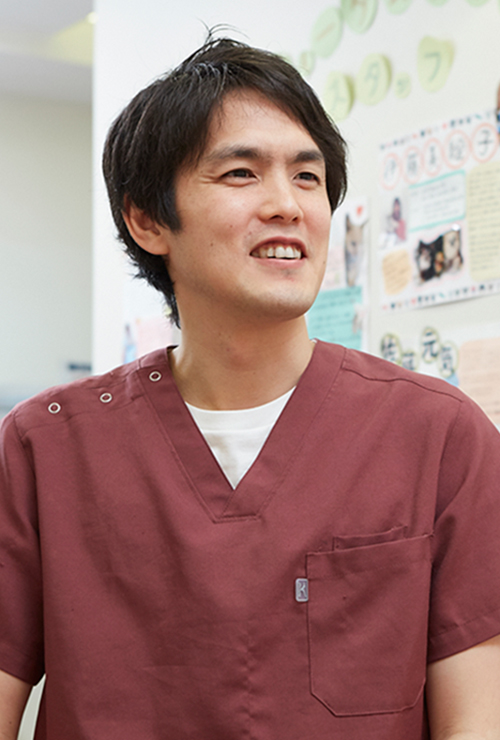

ヴィータ動物病院 地図を見る
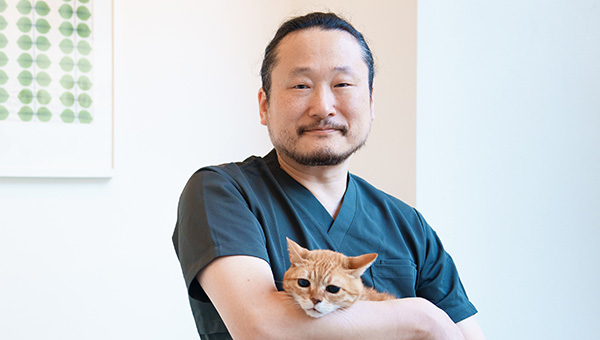
ジェネラリストとして幅広い分野で技術を磨き、家族目線でその子にとってのベストを一緒に考えます。
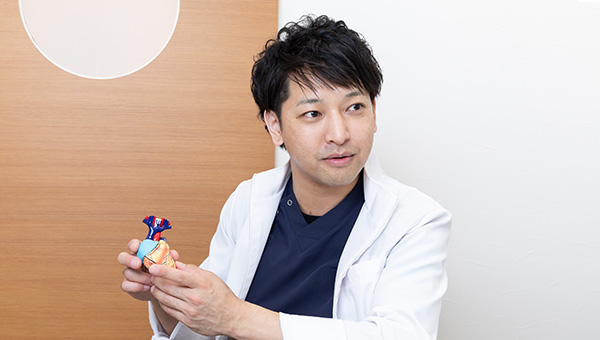
獣医循環器認定医が行う心臓病の治療。犬・猫、飼い主のライフスタイルに合わせた治療を提供します。

体表の悪性腫瘍に電気パルスを与え、抗がん剤の効果を局所的に増強する「電気化学療法」を提供しています。